アコルデ最新仕様をご紹介するシリーズの続きです。
前回、建物価格の話題を挟んで中断した設備仕様の紹介を再開します。
今回は、アコルデの標準トイレです。浴室やキッチンと異なり、基本的に一択のようです。
TOTO ウォシュレット ZJ2 CES9153
現在は、TOTOのトイレをアコルデでは標準にしているようです。
わが家が建てた2012年には、LIXIL(INAX)ベーシアVXが標準だったのですが、一瞬ベーシアの後継機種かなと勘違いしそうになったぐらい、よく似た一体型タイプです。

ZJ2 CES9153という機種は、ホームビルダー向け商品のため、メーカーカタログなども見つからず情報が少ないのですが、ハウスメーカーの標準仕様で採用した人が、発信してくれている情報を見かけます。
一般向けと、差別化を図ることで、かなりコスパのよい製品になっているようです。
調べてみると、アコルデの仕様書にも書ききれていない機能もたくさんありました。
写真もあまり見つからないのですが、こちらが比較的綺麗な画像でした。

見れば見るほどベーシアに似てます。
わが家は、タカラスタンダードに水回りを統一することで、割安になるかわりにタカラのセパレートのティモニになったので、この一体型タイプには、かなり憧れました。
しかし、このトイレ、よく見ると想像以上に高機能な商品でした。
余裕のある手洗いボウル
トイレ一体型の手洗い器は使いにくいイメージがありますが、この製品は深々としたボウルで水はねがしにくいようです。

独立型の手洗いボウルでも、こんなに深さがあり広びろとしたボウルは、なかなか無い気がします。

確かにこれだけ深さがあると、しっかり手を洗えそうです。
たっぷリッチ洗浄の水流もどんな感じか気になります。
陶器ってツルツルじゃなかったらしい
トイレに最も重要な汚れの付きにくさやお手入れのしやすさの機能も豊富です。

まず、気になったのがセフィオンテクトという、陶器の表面をツルツルにして汚れをつきにくくする、超平滑化加工機能です。
陶器って、元々ツルツルだと思っていたんですが、そうではなかったんですね。
10年使用後相当の便器にて比較とあるので、もしかしたら初期の陶器はある程度ツルツルだけど、時間が経過すると普通の陶器はザラザラになりやすいのかな?
長期間汚れにくいはいいですねぇ。
続いて、フチなし形状です。

わが家のティモニは、手前部分がフチ無しなのですが、側面はやはり縁があるので羨ましい。
他社でも縁なしトイレもあって人気が高いことがうかがえますが、デメリットもあるようです。
フチ部分が受け止めてくれていた、跳ね返りが便座に直接あたるので、便座が汚れやすくなるそうです。
確かに、わが家も手前のフチ無し部分は、便座の裏が汚れやすいかも。
ただし、この機種の場合、汚れの付きにくいクリーン樹脂や、継ぎ目のない便座を採用しているので、うまくデメリットを相殺していると言えるのではないでしょうか?
トルネード洗浄は、一見すごそうですが、フチなしにしたため、このようにせざるを得ないということなのかなと思ったり。

お掃除リフトは便利だけど裏側が気になりそう
さらに汚れがつきにくくするために、わざわざ霧を吹いてくれる「プレミスト」という機能があるようです。

トイレが乾燥している状態だと、汚れが付きやすそうなので、意外に効果があるかもですね。

便座が持ち上がる機能は、他社でも当たり前のもはや必須といえる機能ですが、気になるのが上から見えない裏側の様子です。

わが家は、セパレート型なので、裏返してお手入れできるのですが、結構裏側に跳ね返った汚れを落とすのに苦労しています。
ここの汚れ方を知ってから、私は決して自宅では立って小をしなくなりました(笑)
CES9153 機能一覧
わかりやすい機能一覧もあったので貼っておきます。

節水性能は、従来タイプから70%の節水だそうです。

わが家のティモニは、約58%節水だったのでかなり違いますね。

ところで、この従来品13Lって基準、10年前と同じみたいですが、いつまで使うんだろう(笑)
壁から離れるタオルリング
地味なポイントですが、タオルリングの仕様も重要です。
Y51Rというタオルリングが標準のようですが、気になるのは壁からどのくらい離れるかです。

以前、わが家のタオルリングを取り替えたことをブログに書きましたが、タオルが壁に触れているところにカビが出てしまいました。
このタオルリングは、織部から45mm離れる仕様ですが、わが家の当時の標準のタオルリングは、28.5mmだったので良くなっています。

ちなみに、わが家が交換したタオルリングもTOTO製のYHT100 でした。

取り付けて横から見たらこんな感じです。

このタオルリングは、51mm離れているので、より壁から遠くなります。

念の為、調べてみると、INAX(LIXIL) のFKF-AB70Cが、さらに壁から離れているようです。

見た目は、このテカテカしたのより、TOTOのつや消しのほうが好みなのですが・・・
55mmも壁から離れるようです。

YHT100 より倍ほど高いのですけどね。
こんなポイントで、タオルリングも選んで見るのはいかがでしょう?
おまけ:トイレそのもの以上に重要だと思う施工仕様
ところで、おまけですが、住み始めてからトイレのお掃除に影響が大きいと後で痛感したポイントがあるので、取り上げておきます。
それは、止水栓の取り付け方法です。
以前、ブログでも紹介したのですが、わが家はこのようにトイレの止水栓が床に付いています。

しかし、この周りがとてもお掃除しにくいんです。
掃除機やクイックルワイパーのいずれも素直に入らないですからね。
最近は、止水栓の床付は一般的なようですが、以前住んでいた建売では壁付けでした。
ZJ2 (CES9153)の説明書にもあるように、メーカーでも止水栓は壁付けが理想のイメージなのかもしれません。

さらに、電源は、このイラストのように向かって正面の壁につけたほうが邪魔になりません。
わが家は、左の壁に電源をつけたのでケーブルが邪魔で、やはり掃除しにくいのです。
止水栓を壁付けにすることが容易なのかどうかわかりませんが、ご参考ください。
ただし、トイレによっては床付でも目立たないようにできるものもあるようです。
- みんなのWeb内覧会
- WEB内覧会<総合>
- WEB内覧会*玄関
- WEB内覧会*キッチン
- WEB内覧会*洗面所
- WEB内覧会*お風呂
- WEB内覧会*トイレ
- WEB内覧会*階段
- WEB内覧会*ダイニング
- WEB内覧会*リビング
- WEB内覧会<和室>
- WEB内覧会*寝室
- WEB内覧会*子供部屋
- WEB内覧会*書斎
- WEB内覧会*ワークスペース
- WEB内覧会*外構
- ローコスト住宅等の情報&住宅巡り
- 魅力ある家づくり...
- 家づくりを楽しもう!
- いえづくりのこだわり
- 新築・リフォームの間取りアイデア
- 家づくり
- 新築一戸建て
- マイホームブログ
- 住まいと暮らし
- マイホーム、我が家
- DIYブログコミュニティ
- 庭・外構・エクステリア・リフォーム



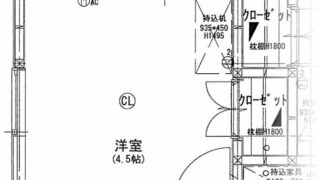













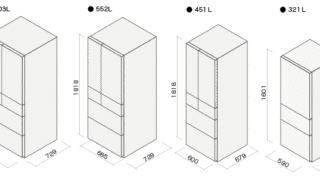











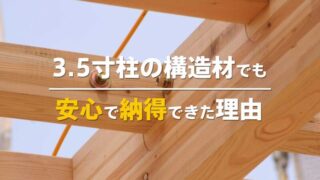
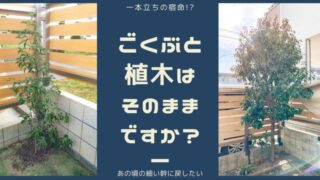

コメント